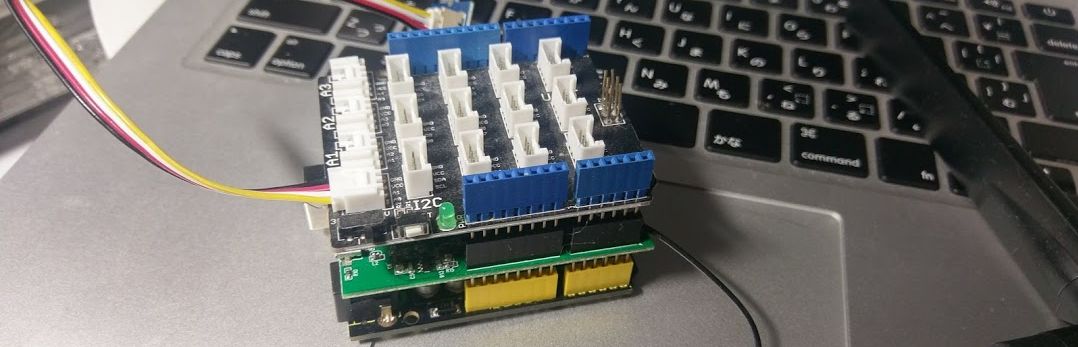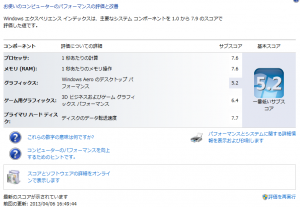2013年4月6日
から hiruta
SZ77R5のストレージをSSDに換装 はコメントを受け付けていません
Shuttle PC 「SZ77R5」をIntel SSD 335 Series(240GB)(¥17,000程度)に換装しました。

PCのハードディスクスロットに固定するための部品も付属しています。ノートパソコンの場合は、固定部品は不要ですが。
Shuttle SZ77R5には、SATA2.0、SATA3.0それぞれ2ポートずつあるので、 SATA 6Gb/s(=SATA 3.0)に対応しているポートに接続。


1TBのHDDをフルにパーティションを使っていたので、EaseUS Partition Master Home Editionで、240GB以下にパーティションを切り直した。
・EaseUS Partition Master Home Edition (ダウンロードはこちら)
その後、EaseUS Disk Copyで、ディスクコピーをしました(240GB)。ディスクコピーするのに1時間30分ほどかかりました。SATAインターフェースをUSBに変換するキットを利用したので、USBの転送速度の分、遅くなったかも。コピー元のディスク容量が大きいと、警告が出ますが、割り当て済のパーティションがコピー先のディスクより小さくしておけば問題ありません。
・EaseUS Disk Copy (ダウンロードはこちら)
コピーしたあと、SSDでシステムを起動し、パフォーマンスをチェックしたところ、プライマリハードディスクのスコアが5.9から7.7にあがりました。ちなみに、グラフィックスの数値がやや低いのは、グラボーは使用していないため。
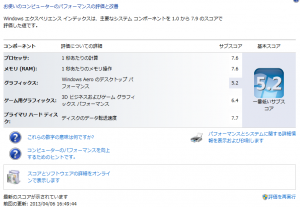
元のHDDをデータ用として、SSDとともに、PCに接続すると、「オンラインである他のディスクと署名が競合しているために、ディスクはオフラインです。」となり、オンライン状態にならない。MBR情報が残っているためかと思われる。MBR情報を含めて、ハードディスクの初期化を行うことで、無事認識させる(オフライン)にすることができました。
diskpartコマンドでオフラインにすることも可能のようです。記事は以下まで。
http://blog.cis1986.co.jp/?p=174