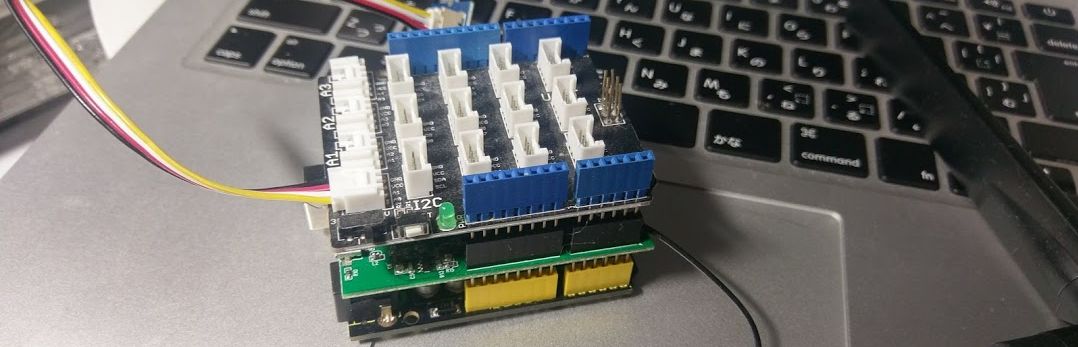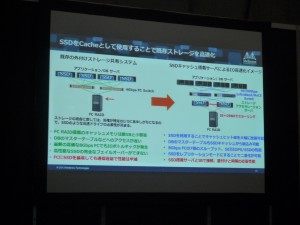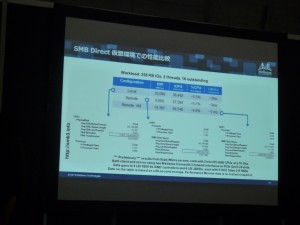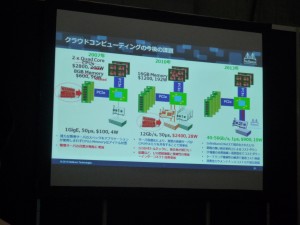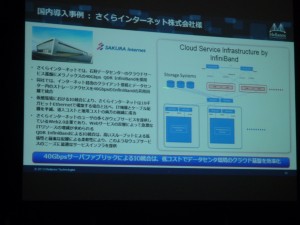ngnixをさくらのVPSにインストール、設定を行いました。
php-fpm、nginxをまず、yumからインストール。(さくらのVPSはCentOS 6.4 64bit)
/etc/php-fpm.d/www.confに、php-fpmをnginxユーザで動作するように設定。
; RPM: apache Choosed to be able to access some dir as httpd user = nginx ; RPM: Keep a group allowed to write in log dir. group = nginx
/etc/nginx/conf.d/default.confで、WordPressのパーマネントためのrewriteの設定を行う。apacheだと.htaccessに行っていたことを行います。
location / {
root /var/www/html;
index index.php index.html index.htm;
if (!-e $request_filename) {
rewrite ^.+?($/-.*) $1 last;
rewrite ^.+?(/.*\.php)$ $1 last;
rewrite ^ /index.php last;
}
}
次は、phpを動作させるための設定です。
location ~ \.php$ {
root html;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/html$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}
httpdを停止させて、php-fpm、nginxサービスを起動させて完了。
ngnixは、ソーシャル系のサービスなど高負荷サイトで利用実績が伸びています。apacheはリクエストごとに、プロセスを起動するのに対し、nginxはひとつのプロセスで行う機構のため、CPU負荷とメモリ使用量を抑えることが可能です。設定ファイルも読みやすい感じです。